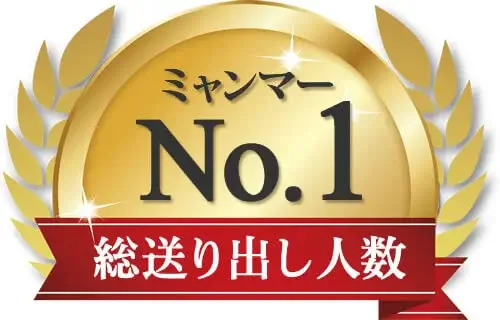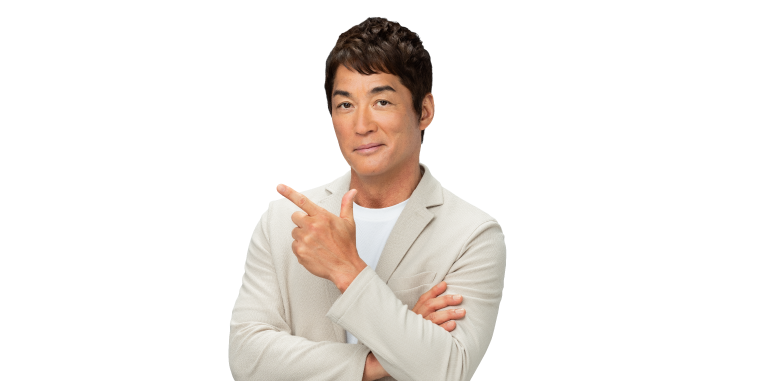「特定技能」ビザ|在留資格特定技能1号・2号の違いを徹底解説<2024年4月12日更新>
2019年4月に新しく加わった在留資格の特定技能ビザについて、そもそもビザ(在留資格)って何?という知識から特定技能1号・2号の違い・取得条件・外国人を雇うことのできる企業・受け入れ機関の条件について解説します。
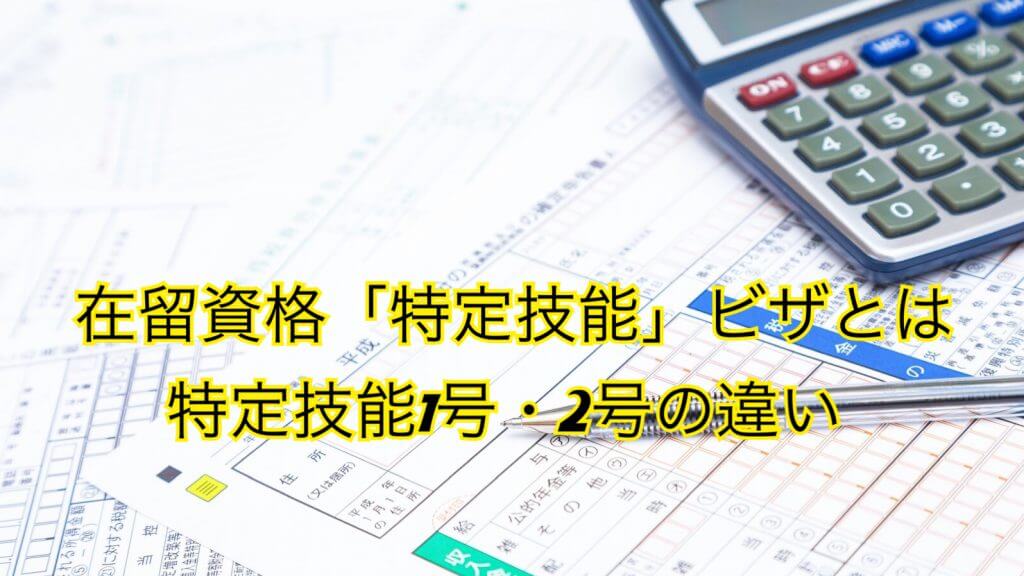
2019年4月に入国管理法が改正し、特定技能ビザが在留資格として新しく加わりました。
以前は外国人が日本で働くハードルがとても高かったのですが、
在留資格「特定技能」が作られたことにより、外国人が日本で働けるチャンスが増えました。
いま日本は、少子高齢化の進行と労働人口の減少に伴い、人手不足が深刻化しています。
そこで、グローバル化の流れとともに日本政府が目を付けたのが、外国人の活用です。
日本人と同じように働いて活躍してもらうことで、労働力不足を補おうという考え方です。
そこで、外国の方が日本で働くための新しい資格、特定技能ビザについてお伝えしていきます。
目次
そもそもビザ(在留資格)って何?
ビザ(在留資格)とは、入国を希望する国から発行されるものであり、入国を認められた人がもらえる資格です。
日本人が外国に入国する場合、その国が日本人に対してビザ取得を要求している場合は、
その国の大使館または領事館を訪れてビザを取得しなければなりません。
さらに、ビザは1種類だけではなく、目的に応じて取得する必要があります。
特定技能ビザとは?
特定技能ビザとは、日本国内で働き手が特に不足している12分野14業種で外国の方が就労するための資格です。
指定されているのは、農業や介護業などの12分野14業種が対象。
指定された12分野14業種は、日本国内だけで十分な社員やスタッフを確保できない現状があります。
そこで、日本人だけではなく、海外人材を積極的に利用していくことで労働力不足を賄おうとしています。
日本でもグローバル化が進む中で、海外の働き手を積極的に雇用し、活躍してもらうという流れは当たり前になりつつあります。
特定技能1号・2号の違い
在留資格「特定技能」は、2種類の資格で構成されています。
1号と2号の特徴や違いについて詳しくお伝えしていきます。
特定技能1号とは?
特定技能1号とは、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する
業務に従事する外国人向け在留資格のことです。
いくら人手不足だからとはいえ、誰でも歓迎というわけではなく、一定の基準を設けています。
また、単純労働も付随する業務であれば可能になりました。
しかし、単純労働のみでの就業はできないので注意が必要です。
在留資格「特定技能1号」は、指定されている12業種14作業全部が対象になっています。
さらに、特定技能1号ビザは在留期間の上限が合計で5年と決まっているところも特徴です。
特定技能2号って?
特定技能2号とは、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向け在留資格のことです。
現時点での対象業種は、介護以外の11分野13業種です。介護職種は「在留資格介護」があるために、特定技能2職種は設定されていません
また、2号ビザは在留期間の上限がありません。
更新回数の制限がないため、条件さえ満たせれば何度でも更新できます。
取得条件について
特定技能ビザは、誰でも取得できる在留資格ではありません。
資格取得の条件があり、いずれかを満たす必要があります。
どのような条件なのか詳細をお伝えしていきます。
日本語評価試験と技能評価試験に合格する
在留資格「特定技能1号」取得条件の1つ目は、試験に合格することです。
外国人が日本で働く場合、即戦力レベルでなければなりません。
そこで、すぐに日本で働けるのかを見定める基準になっているのが特定技能評価試験です。
日本語能力と技術レベルが問われる試験であり、技能評価試験については業界団体ごとのテストを突破する必要があります。
日本語評価試験
日本語能力に関しては、「日本語能力試験」か「国際交流基金日本語基礎テスト」が使用されます。
特定技能ビザを取得するためには、日本語能力試験ではN4以上のレベルが求められます。
国際交流基金日本語基礎テストではA2レベル以上が要求されます。
両方のテストも基本的な言葉や漢字を使って書かれた文章を読んで理解でき、会話もわかるレベルです。
技能評価試験
技能評価試験(技術レベルを見るテスト)は、業界団体ごとで求められる基準が違ってきます。
受ける業界団体ごとに内容をあらかじめ確認しておかなければなりません。
技能実習2号を修了する
技能実習生として3年間の技能実習を修了することでも在留資格「特定技能1号」のが得られます。
技能実習は、日本の技術者が来日してきた海外の方に教えて、
身に着けてもらうことで自分の育った国の発展に寄与するための人を育成するためにある制度です。
日本でOJTをすることで、国際貢献していこうという目的があります。
技能実習生として3年間の技能実習を修了(技能実習の2号を修了)することで、日本で働くことができる特定技能ビザの取得が可能となります。
雇うことのできる企業とは

どの企業も特定技能ビザを取得した外国人を雇用できるわけではありません。
特定技能ビザを持っている外国人を雇うことができる企業や支援をしてくれる機関について詳しくお伝えしていきます。
特定技能所属機関(受け入れ機関)
特定技能所属機関とは、特定技能ビザを取得した海外人材の受け入れ機関のことです。
来日した外国人は、受け入れ機関と直接契約をしてから、仕事を始めていきます。
また特定技能所属機関は、業種別に設けられている協議会に加入する義務があります。
協議会は、外国の方を守る目的に設置されています。
法律や経済情勢の変化などの情報収集や共有をすることや必要不可欠な情報の発信や課題の協議といった役割も担っています。
登録支援機関
登録支援機関とは、外国人の支援計画の作成とサポートを受け入れ機関の代わりに行っています。
受け入れ機関は働きに来る外国人のために、住居の確保や日本語の学びの機会等を与えなければなりませんが、
専門的な知識が不足している企業は登録書類作成などを登録支援機関に委託することができます。
中小企業においては、外国人受入れの環境整備やサポートまで手が回らない場合が多いのが現状です。
外国人受入企業は必ず登録支援機関を利用する必要はありませんが、実績やノウハウがない場合は全部または一部委託することができます。
受け入れ機関の条件
特定技能所属機関として許可されるにも条件に適しているかが問われます。
協議会に参加する義務の他にも、下記の項目を守る必要があります。
・1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
・1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
・欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がない等)に該当しないこと
・報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
・中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり,かつ,役職員の中から,支援責任者及び支援担当者を選任していること(兼任可)等(*)
・外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること(*)
・支援責任者等が欠格事由に該当しないこと(*) など
(注)上記のうち*を付した基準は,登録支援機関に支援を全部委託する場合には不要
引用:法務省「新たな外国人材受入れに関する政省令の骨子」
健全に会社の経営を行っているのであれば、問題なく守っている項目ばかりです。
法律やルール等守っていない企業では、日本人はおろか外国人も働かせたくはないですよね。
また受け入れ機関には、外国の方を雇うための基準というのも設けられています。
①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
②受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が適切であること(1号特定技能外国人に対する支援について)
在留資格「特定技能」で家族帯同はできるのか
次に、在留資格「特定技能」が家族帯同で来日できるのかについてお伝えしていきます。
在留資格「特定技能1号」では家族帯同での来日はできません。
理由としては、は労働力確保が目的の就労ビザなので、家族帯同は原則認められていないのです。
対して在留資格「特定技能2号」は家族帯同で日本に滞在することが認められています。
但し、家族帯同が認められているのは配偶者と子供だけです。
配偶者と子供には家族滞在の在留資格が付与されて、家族そろって日本で暮らすことができます。
特定技能ビザの実情
在留資格「特定技能」での日本在留者数
2023年12月時点での特定技能外国人の数は208,425人となっております。
その半数以上がベトナム人になります。
ベトナムからは大都市出身の大卒者が来日するのではなく、地方部の高卒者が来日するパターンが大半です。
業種ごとでみると、飲食料品製造業と農業で全体の半分以上を占めています。
外国の方を積極的に採用している業種もある一方、進んでいない業種もあるのは事実です。
【完全版】在留資格「特定技能」ミャンマー人材受け入れガイド
さいごに
在留資格である特定技能についてと特定技能ビザ1号・2号の違いについてお伝えしてきました。
外国の方が日本で働きやすくなったとはいえ、まだまだ資格として活かしきれていない面が多くあります。
14種類の業種が特定技能ビザの対象となっていますが、業種によって活用状況に差が出てきています。
日本の少子高齢化、労働力不足は喫緊の課題です。
日本の持続的繁栄のためにも、現在の在留資格「特定技能」の課題が解決され、
日本のため、そして日本で働きたい外国人のための制度に改善されることが望まれます。
無料でご提供しております